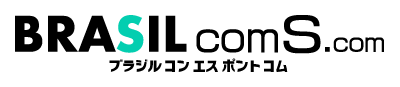アマーロ・フレイタス【インタビュー】 多様なブラジルを知る、伝える:音楽を通じた世界との対話
4回目の来日を果たされたアマーロ・フレイタスさんにブラジル音楽・文化的な視点からインタビューをさせていただきました。
自身の生まれ育ったブラジルの自然や文化的ルーツを大切にしながらも、特定の地域や音楽ジャンルに収まらない活動を展開するアマーロさんのアーティストとしてのバックグラウンドから今後の活動の方向性まで様々なお話を伺うことができました。

撮影:Micael Hocherman
聞き手:鈴木岳志 構成:Willie Whopper 協力:Blue Note Tokyo
Q: アマーロさんが日本に来たのは今回で4回目になりますが、もう日本には慣れましたか?それとも未だ何か難しさを感じることはありますか?
A: 日本に来るたび、この土地とともにより多くのことを学んでいます。しかし、最も私の関心を引くのはここで感じるエネルギーです。おそらくあなたたち日本人にとってそれは普通のことなのでしょう、ここで生まれたわけですからね。でもそれは私にとっては異質なものです。ブラジルにいる時、私はカオスのエネルギーを感じます。一方、日本では秩序のエネルギー(energia da organização)を感じます。たとえば、日本でも車が走っていますが騒音を出しません。ここはたくさんの建物がある大都市ですが、道にはゴミが落ちていません。世界はもはや純粋ではないけれど、あなたたちはある種の純粋さを持っているかのようです。チャクラのバランス、禅的なものです。そんなエネルギーを感じます。なので、ここではよく眠り、食べることができています。人々からのリスペクトを受け、自分に尊厳があると感じます。これがここに来るたびに強まっていく、(日本に対する)印象です。もちろん、まだまだ発見すべきことはたくさんあります。でもそれは自分の時間、経験を通して発見していけることだと思います。
Q: 今回の来日メンバーを紹介していただけますか?
A: サンパウロのベーシスト、シヂエル・ヴィエイラとサンパウロのドラマー、ホドリゴ・ヂガォン・ブラスです。二人ともサンパウロの音楽学校の先生です。彼らと組む前に日本に来た時はフランス・パリ出身のドラマー、フランソワ・モランとキューバのアニエル・ソメイランのトリオで演奏しました。また、私の最初のトリオ、つまり最初の3枚のアルバムを録音したメンバーはベースにジーン・エルトン、ドラムにウーゴ・メデイロスでした。その後、仕事の都合によってメンバーを変更することになり、彼ら二人の素晴らしいミュージシャン(今回のメンバー)と仕事をすることになりました。
Q: どのような経緯で彼らを知ったのですか?
A: 私はもともとシヂエルの大ファンでした。彼は既にブラジルのたくさんの音楽家の伴奏をするベーシストでしたからね。ホーザ・パッソスのバンドやダニ・グルジェウ、セザール・カマルゴ・マリアーノ、ピアニストのアミルトン・ゴドイ。あとはエドゥ・ロボもですね。これらの名前を見ただけでも彼がブラジル音楽シーンにおいて存在感をもった音楽家であることがわかりますよね。こういうわけで私はずっと彼と仕事がしたかったのですが、これまでは予定が合わず実現しなかったんです。
ヂガォンのことはヴィトール・カブラウというサンパウロのドラマーを通して知りました。ある時、ヴィトールがフェスティバルで演奏できなかったとき、代役としてヂガォンが演奏したことがありました。その時私は、彼がどれほど万能でドラムという楽器を極め尽くしているのかを目の当たりにしました。また、彼は非常に協調的な人物であることもわかりました。だから、彼に「私のバンドでドラムを叩かないか?」と声をかけたんです。

Q: これまでのトリオと比較して、現在のトリオにはどんな特徴があるのでしょうか?
A: 私の最初のトリオはジャズの中にクラシック音楽的なサウンドを持ち込むようなグループでした。たとえば、ドラマー(ウーゴ・メデイロス)はまるで「一つの曲」を作るかのように演奏を捉えていました。彼の演奏はいわゆる慣習的なものではなかったのです。「よし、ファンクのグルーヴだ!」「サンバだ!」「フォホーだ!」ということではなく、彼はいつでも新しいリズムを創造していたんです。それらはとても難解でした。何故ならば全てのものがポリリズム、イソリズム、ネガティブ・リズムと結びついていましたから。足は5拍子を、右手は3拍子を、左手は4拍子を刻み、彼はこのポリリズムの上にグルーヴを作り上げたのです。それは何一つ自明のものはない、非常に複雑なものでした。その一方で、彼が即興をすることはほとんどありませんでした。
私が感じるのは、ヂガォンはそうした「音の建築家」ではないということです。彼は「一つの曲」を作り上げるタイプのドラマーではないのです。けれども、ヂガォンは非常に優れた即興演奏家です。さらに、彼はブラジル音楽の要素を取り入れます。シェイカー(ovinho)、パンデイロなど、こうしたブラジル音楽を構成する異なる要素を用いて演奏するドラマーなんです。
Q: あなたはブラジル音楽のミュージシャンとしてのアイデンティティと、ジャズ・ミュージシャンとしてのアイデンティティの両方を持っています。それら二つの世界はどのように共存しているのでしょうか?
A: 私の人生に最初にやってきたのはジャズでした。私は周辺地区(periferia)出身です。ブラジルにおける周辺地区とはつまりファヴェーラ(スラム)、都市の外縁です。私はそこで生きることが悪いものであると言いたくはありません。しかし、ブラジルにおける周辺地区とはファヴェーラであり、生活が大変な場所なんです。
こうした場所では、たくさんの人が福音派の教会に入ります。私自身、福音派の教会でドラムをはじめ、そのあとピアノを弾くようになりました。ある時、教会の友だちがジャズのDVDをくれました。それこそ私が15歳の時、はじめてジャズを聞いた瞬間でした。それはチック・コリア・トリオでした。チック・コリア、ジョン・パティトゥッチ、デイヴ・ウェックルによるニューヨークのブルーノートでの演奏でした。それを聴いた時、「なんてこった…なんだこの音は…」という気持ちになりました。それは私が教会で弾いていたものとは全くの別物だったんです。その時から、チック・コリアのアコースティックバンド、エレクトリックバンド、チック・コリアがデイブ・ホランド、ロイ・ヘインズ、エディ・ゴメス、ジャック・ディジョネット、マイルス・デイヴィス、ハービー・ハンコック等と演奏したものを聴き始め、その後、セロニアス・モンク、セシル・テイラー、ジョン・コルトレーンなどのジャズを聞くようになりました。
大学に入ってからは、私は「私自身の文化」を探究するようになりました。ペルナンブーコのたくさんのリズムについて学ぶようになったのです。それら全てが私を変革しました。言うなれば、「それこそが私(eu sou isso)」であるからです。マラカトゥ、バイアォン、コーコ、シランダ、カボクリーニョ、カヴァーロ・マリーニョ、フレーヴォ等、たくさんのペルナンブーコ由来のリズムがあり、私はその一部であるように感じました。
以降、それら伝統的なペルナンブーコの音楽とジャズを融合させる音楽家たちの存在を知ることになります。たとえば、ナナ・ヴァスコンセロス、モアシール・サントスなどです。ショーロ好きに向けて言うならば、チア・アメーリア、カピーバもいますね。私は彼らの音楽を学び、ペルナンブーコの音楽と他のスタイルを一つにする方法を知りました。
Q: つまりあなたは北東部の音楽を弾く前にすでにジャズを始めていたんですね。
A: そうですね。レシーフェにあった複数のクラブで既にジャズを演奏していました。ちなみに、私の最初の3枚のアルバムでドラムを演奏したウーゴと知り合う以前から、ジーン(・エルトン)とはたくさんのクラブで一緒に演奏していました。それはとても面白い経験でした。オスカー・ピーターソンというピアニストがいますが、彼はピアノとベースのデュオで演奏することを好んでいました。私はジーンとのデュオにおいてどのように演奏するかを探るため、オスカー・ピーターソンのデュオ編成のアルバムをたくさん聞きました。他にも、同じようにデュオで演奏することが多かったミシェル・ペトルチアーニのレコードもたくさん聞きました。こうして私は様々なバーやクラブでジーンと演奏したわけですが、それらはデュオ演奏を学ぶ実践の学校のようでした。その後、ウーゴと知り合ってからは、ポリリズム、イソリズムそしてペルナンブーコのリズムを一つにしたサウンドを創り出すべく、毎週、彼らとともに演奏を通して学びました。
Q: 私が今夏レシーフェを訪れたとき、たくさんのショーロの音楽家がフレーヴォのブロコ(カーニバル期に街路を練り歩きながら演奏やダンスのパフォーマンスをするグループ)に所属しているのを目にしました。あなたもフレーヴォのブロコに入っていたことなどはあるのでしょうか?
A: 私はいつでもレシーフェのカーニバルを愛しています。カーニバルのオープニングや、フレーヴォの拠点で演奏したこともあります。しかし、ブロコで演奏することに関しては、ピアノを運搬する術がないので難しいです。パーカッションを学んでフレーヴォのブロコに参加しようかと友達と話したこともあります。しかし、ブロコで演奏したことはありません。けど、彼らと一緒にパレードで歩いたことはありますよ。
Q: あなたのアルバムを順に聴いた印象ですが、枚数を重ねるごとに典型的なブラジルのリズムではなく、より新しいサウンドを目指しているように感じました。この4枚目のアルバムの次はどこへ向かうのでしょうか?
A: あなたが聴いてくれた一連のアルバムはいわば私の軌跡を語るものです。『Sangue Negro』は私がレシーフェに生きた時、『Rasif』は私がレシーフェを「知った(conheço)」時と対応しています。ここで私の故郷(レシーフェ)についてお話しましょう。『Rasif』はレシーフェの語源となった言葉なんです。これはアラビア語です。レシーフェの土地にはポルトガル人、そしてアフリカ系の人々がいました。また、そこには先住民たちもいました。さらにたくさんのアラブ人やユダヤ人もいました。これらの内、レシーフェのセルタォン(ブラジル北東部の奥地)の伝統はアラブ人にあるんです。たとえば、ハベッカ(口ずさむ)、そしてメーザ・ヂ・グローザ(口ずさむ)。これらはアラブのものです。
(こうした歴史を知り、)私はアラブと先住民のものであるこの土地についてもっと理解したいと思うようになりました。ペルナンブーコの語も元は先住民の言語トゥピ・グアラニーの語「パラナンブーコ」から来ています。パラナンブーコの意味は「砕ける海(mar que arrebenta)」です。こうして、レシーフェの音楽の理解に取り組むようになった時、私の土地に捧げる詩のようなものとしてアルバム『Rasif』をつくりたいと思ったんです。
そういう中で「Trupé」(同アルバムの二曲目)も生まれました。「Trupé」はコーコというリズムの一種です(リズムを手拍子と口で表現)。このコーコはセルタォンからきたものです。最初のセルタォンの都市はアルコ・ヴェルヂというところでした。そこにはコーコ・ハイーゼス・ド・アルコ・ヴェルヂというグループがいます。彼らはサンダルをはいて、木の檀の上で踊ります。そこで刻まれる床を踏み鳴らすリズムは伝統的なコーコとは異なっています。私はこのリズムをイソリズムに変換し、「Trupé」を作りました。このように、このアルバムはこの土地についての作品となりました。すでにイソリズム、ポリリズムが含まれてはいますが。
3枚目のアルバムのタイトルになった『Sankofa』はアフリカ由来の語です。これは私がヨーロッパやアメリカ合衆国で演奏を始めた時期と対応した作品でした。それらの地域で演奏する中で、私はアフリカのディアスポラを知りました。そうして私はその中での出会いとディアスポラについて語るこのアルバムをつくったんです。何故なら、ブラジルにおいてアフリカ系の人々が自身の歴史について学ぶことは当たり前ではないからです。歴史を書いてきたのはいつだってヨーロッパ人でしたからね。こうしたことから、少し前から、私の前に生きた人々の歴史は何なのか、私は誰なのか、私の祖先は誰なのかを問い直す運動が始まりました。テレーザ・ヂ・ベンゲーラ、(マホマ・ガルド・)バクアクア、カズンバ、ミルトン・ナシメント、サンバ・ド・パルチード・アウト、これら全てがこのアルバムには詰まっています。
このアルバムの後にできたのが『YY』です。私ははじめてアマゾンを訪れました。あなたが韓国や中国に行ったことがないのと同様、アマゾンに加え、ペルー、コロンビア、エクアドルといった他の南米諸国に行ったことがないブラジル人はたくさんいます。けれど、これらの場所にいったことのないブラジル人でもヨーロッパには行ったことがあるんです。自身の近隣の国に行くよりもヨーロッパにいくことはずっと一般的なことなんです。そういうわけで、はじめてアマゾンに行った時、私は異なるブラジルを発見しました。異なる顔つき、異なる食べ物、異なる知識、異なる自然との関係の結び方、それは私の人生で一度もみたことのないものでした。私はそれらに大きな衝撃を受けました。その時、私はこの土地の伝説と、この場所がどれだけ美しいかを伝えるアルバムをつくりたいと思ったんです。私はこのアルバムを通して「私たちはアマゾンを保護しないといけない」「私たちは私たちの海を守らないといけない」「私たちは私たちの惑星を守らないといけない」と叫ぶ必要がありました。このアルバム『YY』はプリペアドピアノというピアノの弦を直接演奏するジョン・ケージの拡張的なテクニックによってつくられていますが、私が経験したアマゾンにおける「生(vivência)」から生まれた作品なんです。
『Sangue Negro』を除く3枚のアルバムは脱植民地的なアルバムであるといえます。それらのタイトルは一つも植民者の言葉ではないからです。ポルトガル語、英語、フランス語、イタリア語、そのどれでもなく、アラビア語、アフリカの言葉、先住民の言葉です。なので、私にとってこれらの仕事は「ブラジル自身にもまだ紹介されていない、別のブラジルの物語を語ること」についてのものなんです。私が滞在しているホテルにかけられているハービー・ハンコックの写真の下にジョイス・モレーノの写真が並べられているのを見るとき、こう思うんです。あなたたち(日本人)が知っているこのブラジルを、ブラジル人自身は知らないんだ、と。だから私にとって、とても大事なのは日本の人たちと対話をすることなんです。そして「私の音楽の中にこんなに美しいブラジルがあるんだよ」と伝えること。でも同時に、ブラジル人にもこう言いたい。「私たちにはこんなブラジルがある。これこそが私たちのブラジルであり、私たちの宝物なんだ。このブラジルを守らなければならない」と。
あなたは新しいコラボレーションについて尋ねましたね。それらは、いま私が録音しているアルバムの中で実現します。それらの新しい共演は、内側から出てくる内臓のような部分、もっとも深いところを表すと同時に、より広がりをもった部分も表すものになるでしょう。なので、次のアルバムには日本からの参加者もいます。
Q: なんと!そうなんですか!
A: はい。他にもペルナンブーコの先住民コミュニティから、アメリカ合衆国から、そしてアフリカからもアーティストが参加します。私が世界で知り合ったそうした人々が混ざり合ったアルバムになるでしょう。
Q: あなたが特定の地域だけでなく、世界のあらゆる人たちと共同しながら創作を続けていることに感動しました。そして日本もあなたにインスピレーションを与えられていることを嬉しく思います。
A: もちろんです。日本からはたくさんのインスピレーションを受けました。次のアルバムでは少なくとも2曲、日本人と演奏した曲が入ります。3曲になるかもわかりませんが、2曲は確実です。私は日本でたくさんの人と知り合いました。小曽根真とも知り合いましたし、(上原)ひろみの大ファンでもあります。歌手のかほ(中村佳穂)、そしてダンサーのかほ(小暮香帆)とも知り合いました。歌手であり、音楽家でもある青葉市子とも知り合いました。日本に来るたびにこういうふうに人と出会うのが好きなんです。
Q: あなたの話を通して、あなた自身の軌跡を知ることでアルバムをより深く聴けるように感じます。あなたのキャリアにとって重要な参照点となっているブラジル国内、国外の音楽家を教えていただけますか?
A:(ブラジル)国外だとジョン・ケージ、チック・コリア、ゴンサロ・ルバルカバ、エリック・サティ、ショパン、セロニアス・モンク、セシル・テイラー、Viji、マッコイ・タイナー、ハービー・ハンコック、キース・ジャネット、ブラッド・メルドー、アブドゥーラ・イブラヒム、チューチョ・バルデース、ミシェル・カミロなど。好きなアーティストがたくさんです(笑)
国内だと、タニア・マリーア、ジョアン・ドナート、ドン・サルヴァドール、ラエルシオ・ヂ・フレイタス、レチエレス・レイチ、ルイス・エサ、セザール・カマルゴ・マリアーノなどです。あとは誰も知らないけどトニー・ユカタンが好きです。ジョニー・アルフも大好きですよ。
Q: エルメートが最近亡くなりましたが、彼もあなたにとって重要なレファレンスとなっているのでしょうか?
A: そうでした!もちろんエルメート・パスコアルとエグベルト・ジスモンチは重要です。彼らの重要性はあまりにも自明なので、言い忘れてしまうことがありますね。
Q: 日本にもたくさんのエルメートのファンがいますが、なにかコメントをいただけますか?
A: 僕にとってエルメート・パスコアルという人は、あらゆる可能性の化身そのものなんです。アラピラカというアラゴアス州の内陸部の小さな町の出身で、本当にいろんな困難を経験してきた人です。ですが、彼はその苦しみによって自分の中にある音楽を止めることはなかった。僕にとってエルメート・パスコアルは、「世界の音楽」と「ブラジルの音楽」、「即興の音楽」と「自然発生的な音楽」、「奇抜な音楽」と「古典的な音楽」、「攻撃的な音楽」と「穏やかな音楽」、それらすべての接合点のような人です。彼はピアノを弾いてとても繊細なメロディーを生み出すこともできるし、でも同時に、水の入ったボトルや、子ブタ、メガネでも音楽を作れてしまう。あるいはあなたを呼んで、そのカップに水を注ぐよう頼み、その音で音楽を作るかもしれない。外に出て、風と戯たり、川に入って、そこで音楽を作ることもできる。「私は音楽そのものだ」と彼自身が言っていました。そんな人物がブラジルから、そうした地域から生まれたというのは本当に稀有なことだと思います。だから僕はすべてのブラジル人はエルメート・パスコアルという人が自分たちの国に生まれたことを誇りに思うべきだと思います。そして、彼のコンサートを見ることのできたすべてのエルメート・ファンは魔法使いエルメート・パスコアルが音楽を生み出す日に立ち会えたことを誇りに思っていいでしょう。
Q: 美しいコメントをありがとうございます。あなたと同世代のピアニスト、エルクレス・ゴメスとサロマォン・ソアレスについてもなにかコメントをいただけますか?
A: もちろんです。エルクレスはサンパウロに住んでいるものの、エスピーリト・サント出身です。僕はエルクレス・ゴメスという人は、ブラジルの伝統音楽、ショーロ、マシーシ、フレーヴォといった音楽をとても深い形で甦らせている人物だと思います。彼はその仕事とともにブラジル各地を回っており、同時に研究的な活動もしている。エルクレス・ゴメスは私たちのコンテンポラリーなブラジル音楽において欠かせない存在です。私は彼の仕事の大ファンです。
サロマォン・ソアレスはパライーバ出身です。パライーバはペルナンブーコのご近所です。なので彼は私の兄弟のようなものですね。彼はブラジルのジャズにおける発明的なピアニストです。彼は色んな顔を持っていて、たくさんのサロマォンが存在するんです。ソロピアノ、トリオ、そして私の大好きな歌手、ヴァネッサ・モレーノとの仕事もあります。アミルトン・ヂ・オランダ・バンドでの仕事もありますね。あまりにも巨大な創造性をもっていることから、彼の音楽を聴くとソロで弾く時、アミルトンと弾く時、ヴァネッサと弾く時、トリオで弾く時で色んなサロマォンを知ることになります。それらは同じではないんです。彼はそれぞれの仕事において異なる個性を表現できる。それでいて彼は、どんなスタイルでもオリジナルな音を持っている。聴けばすぐ「これはサロマォンだ」と分かるけれど、同時に「(他のプロジェクトで演奏する時と)全然違う!」とも思わせる。彼はとても技巧的で、勉強熱心なピアニストですし、今後もきっとブラジル音楽に偉大な作品を残すだろうと思います。
Q: 彼はザブンバ(フォホーなどの演奏に用いられる太鼓)とピアノのアルバムも出しましたよね。
A: そう!ピアノとザブンバのデュオ。伝統的な編成はアコーディオンとザブンバなんです。でもサロマォンはピアノとザブンバでやったんです。アミルトン・ジ・オランダとのトリオでは、左手でベース・ラインを弾きながら、右手で即興するんです。それも本当に素晴らしい。
他にももう一人、私たちの世代における重要な人物がいます。彼はピアニストではありませんが、私にとっては私たちの世代における天才です。エンヒーキ・アルヴィーノです。彼はフルート、サックス、ピアノ、弦楽器を演奏するマルチ奏者であるだけでなく、素晴らしいアレンジャーなんです。僕が最近ブラジルでやった「ペルクルソ・アンサンブル」というオーケストラとの共演では、アルビーノがアレンジを担当しました。それから、私には歌手リニケルとの共演曲もありますが、その曲「Ao teu lado」はグラミー賞のベストレコーディングにノミネートされました。そのストリングス・アレンジもアルビーノによるものです。リオの歌手、フーベルの新作でもオーケストラのストリングアレンジを彼が手がけています。
今、僕は新しい7人編成のグループを組んでいて、すでにブラジルで2回公演しましたが、そこでもアルビーノが演奏しています。彼はファンタスティックな音楽家で、世界はまだ彼を知らないけれど、彼はいずれブラジル音楽界のレチエレス・レイチのような存在になると思います。
Q: 最後に若いブラジル音楽ファンに向けてメッセージをお願いできますか。
A: ショーロ、フレーヴォ、サンバをたくさん勉強してください!これらは少なくともブラジルをよく表現した音楽です。なので、もしこれらの音楽を演奏するならば、それはブラジルの歴史をある形で守ることになります。ブラジルにはたくさんの音楽と文化があります。しかし、ショーロ、サンバ、フレーヴォを学べば、ブラジルを表面的にではなく、深く知ることができます!
Q: どうもありがとうございました!
追記:アマーロさんはとても穏やかで、同時に好奇心旺盛な方でした。インタビューが始まる前から日本の人々や文化についてさまざまな質問を投げかけてくださり、その姿勢からは「自分の演奏を聴いてもらう」だけでなく、「自分の知らない日本をもっと知りたい」という真摯な思いが伝わってきました。そのやりとりを通じて、私自身が日本について改めて考えさせられました。インタビューの前に「日本で洋服を買いたい」と話していらしたので、取材場所であるブルーノートのすぐ近くにある「SOU・SOU青山店」をご紹介しました。とても気に入ってくださったようで、インタビュー後に早速購入され、翌日のブルーノート・ジャズ・フェスティバルではその服を着用されていました。ご本人のInstagramでも、そのことについて紹介されています。

アマーロ・フレイタス
1991年ペルナンブーコ州・レシーフェ生まれ。ピアニスト、作曲家、アレンジャー。ジャズとブラジル音楽を基礎に国際的な活動を展開。今回で4回目の来日。