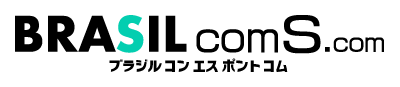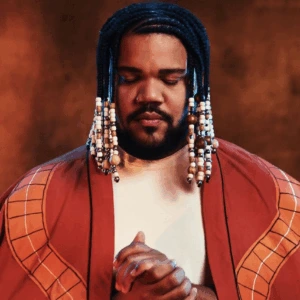ブラジル音楽ショーロ完全ガイド:第0回 イントロダクション
はじめに

出典: Rodrigo S. Maior (2023). Laranjeiras – Praça do Choro – Rua General Glicério. Wikimedia Commons, CC BY 4.0
みなさんはショーロ(Choro)という音楽をご存知でしょうか。
十九世紀のリオ・デ・ジャネイロに起源を持つとされるブラジルのインストゥルメンタル音楽です。
軽快なリズムの楽しい曲から、ゆったりとしたテンポの叙情的な曲までそのレパートリーは多様であり、演奏において即興的な性格を持つことから「ブラジルのジャズ」なんて呼ばれることもあります(あまり良い呼び方ではない気もしますが!)。
サンバやボサノヴァほどの知名度はないものの、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本にも多くの愛好者を持つ国際的な人気を誇る音楽です。
楽器としては主にフルート、ギター、七弦ギター、カヴァキーニョ、バンドリン、パンデイロなどが使用されます。
数あるレパートリーの中でもとりわけ一般に知られているのは「Carinhoso」(カリニョーゾ)と「Tico Tico no Fubá」(チコ・チコ・ノ・フバー)です。
前者は「ブラジル第二の国歌」と呼ばれるほど、ショーロの枠を超えて人々に愛されていますし、後者はディズニー映画『ラテン・アメリカの旅』に使われているので耳馴染みのある方も多いのではないでしょうか。
実は日本でもカフェ、デパート、TVのBGMとしてショーロが流れていることがあります。
ぜひ耳を澄ましてみてください。
申し遅れました。
私は東京外国語大学大学院でブラジルポピュラー音楽の研究をしている鈴木岳志といいます。
修士課程ではショーロの歴史を主題に学位論文を執筆し、現在も引き続き博士課程でショーロの研究に励んでいます。
今回はBrasil com S.さんから提案していただき、ショーロについての連載コラムを書かせていただくことになりました。
これから数回かけて、ポピュラー音楽研究者の立場からショーロをより深く知るための記事を書いていきます。
ショーロについて語るべきことは無限にあるのですが、この連載では主にショーロの「歴史」についてお話ししていきたいと思います。
音楽の内容だけでなく、その歴史を知ることで、ショーロの楽しみはより立体的なものになるでしょう。
この第0回ではイントロダクションとして、本連載の「ショーロの歴史」に対するスタンスを示したいと思います。

出典: Choro Music (2006). Instrumentos choro. Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
本連載のコンセプト:「役に立つショーロ史」
この連載では「役に立つショーロ史」をコンセプトに、ショーロの歴史を書いていきたいと思います。
このようなコンセプトを掲げるのは、近年のブラジルポピュラー音楽研究の知見を踏まえれば、「正しいショーロの歴史」或いは「単一のショーロ史」なるものを確定するのは難しいからです。
その理由は第一にショーロの「歴史的事実」を確定するための史料が十分に残っていないこと、そして第二に、こちらがより重要なのですが、文字によって普及している「ショーロの歴史」はその限られた資料をもとに、後の時代の人が「過去を語り直すこと」によって作られてきたものだということです。
こうした「歴史」は「過去そのもの」が蓄積されることによって成立したのではなく、ラジオの司会者、ジャーナリスト、批評家、研究者、音楽家などの語り手が、それぞれ固有の文脈の中で過去の史料を再解釈し、普及させることで形成されました。
そこには当然、広める人のバイアスや意図が含まれます。
つまり、ショーロの歴史には時代や地域、執筆者によって多様なヴァージョンがあり、そうした複数性を無かったことにして「単一のショーロ史」を打ち出すのは難しいのです(もちろんこれらの「歴史」が「間違っている」わけではありません!)。
近年のショーロ研究はこうした特定の時代の特定の人々によって広められた「わかりやすい歴史」からは抜け落ちてしまうようなショーロの多様性に注目しています。
例えば、「ショーロの伝統」の歴史的変遷、古いショーロの音楽家たちの楽譜の流通網、ショーロとマスメディアの関係、ショーロとブラスバンド文化の関係、ショーロのリオ以外の地域における実践などです。
ショーロの歴史はこれからもこうした多様性への注目とともに更新されていくでしょうし、その可能性を閉ざさないためにも、「正しさ」や「単一性」を打ち出すのは良くないと考えました。

出典: Gilberto Marques (2019). Choro, Chorinho e Chorões. Wikimedia Commons, CC BY 2.0
とはいえ、ひとまず「ショーロの歴史」とはこういうものだと言われているものを示すことは可能ですし、それには意味があります。
そこで思いついたのが「役に立つ」というコンセプトでした。
私がこの連載で語っていくのはショーロの複雑性を理解する補助線として「役に立つ」、典型的な「ショーロ史」です。
これからも様々な形で語り直され、更新されていく暫定的なものではありますが、ひとまずショーロの歴史として共有されている「型」のようなものをお伝えしていきたいと思います。
もちろん、「役に立つ」からといって「何でもあり」にしてしまうわけではありません。
ショーロの語りには多様な可能性があることを認めた上で、ブラジルで参照されているテキストに基づきながら知っておいた方がよいと思われるポイントに楔を打っていくという意味です。
きっとショーロを聞く時、ショーロの音楽家たちと話す時に役に立つ知識となると思います。
途中で計画が変わることもあるかもしれませんが、以下のようなことをお話ししていきたいと考えています。
1.ショーロ前史
2.十九世紀終盤〜二十世紀初頭のショーロ
3.1930年代頃:ピシンギーニャ
4.1940〜1960年代:ジャコー・ド・バンドリン
5.1970年代:ショーロリバイバル
6.1990年代〜現代
おわりに
現代の日本において、音楽は主にCD、サブスクリプションサービスそしてソーシャルメディアによって特定の規格に収められた「商品」「作品」「コンテンツ」として流通しています。
しかし、ショーロを知ることはそれらの限られた情報を消費することとイコールではありません。
一口に「音楽」と言っても背景にはそこに生きる人々の社会、文化があります。音楽は「世界共通言語」などといわれがちですが、実際は常にローカルな性質を持ちます。
ショーロの歴史を知ることでそうした音楽文化の多様さ、当たり前と思っていた価値観からはみ出す音楽の面白さと出会っていただけたら嬉しいです。
今回は連載のスタンスを示すだけで字数がいっぱいになってしまいました。
次回はショーロの基礎的な情報と、その黎明期のお話をしていきたいと思います。