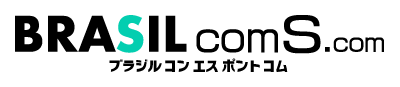【特集】中原仁さんに伺う「まだブラジルという言葉を知らなかった頃。音だけが、先に心へ届いた」

ブラジル音楽と向き合うとき、大切なのは難しい言葉でも、技巧的な説明でもない。
必要なのは、音と人に対して、まっすぐに言葉を置くこと──。
50年前、ミルトン・ナシメントの声に心を撃ち抜かれて以来、ラジオとレコーディングの現場でブラジル音楽と向き合い続けてきた中原 仁さんに、ブラジルに関心を持つ若い世代に向けてメッセージをいただきました。
ブラジル音楽と向き合うとき、言葉はまっすぐでいい
数々のブラジル人ミュージシャンたちと実際に向き合い、レコーディングやライブの現場で対話を重ねてきた中原さん。
番組制作という枠を超え「音楽制作の現場」に身を置いてきたからこそ感じることがあるという。
「ブラジルとそれ以外の国の違い、という言い方が正しいかはわかりませんが、少なくともブラジル人とコミュニケーションを取るときは、日本的な回りくどい言い方はしない方がいい。
ストレートに話すこと。それが一番だと思います」
通訳を介する場面も多い中で、言葉の構造が曖昧な日本語は、ときに相手を戸惑わせてしまうという。
「主語と述語がはっきりしない質問って、記者会見でも本当によくあるんです。
何を聞きたいのか分からない。通訳の方が困ってしまう場面も少なくありません」
翻訳ソフトが当たり前になった今日だからこそ、むしろ日本語の特性がより浮き彫りになるという。
「一度日本語をポルトガル語に翻訳して、さらに日本語に戻してみると、驚くほどストレートな文章になることがあるんです。
日本語がいかに持って回った表現をしているか、よく分かると思います」
ブラジル音楽の現場で必要なのは、技巧的な複雑な表現ではなく、率直な意思表示なのだと中原さんは語る。
50年前、ミルトン・ナシメントの声に心を撃ちぬかれた

Native Dancer
ブラジル音楽との最初の出会いは、今からちょうど50年前にさかのぼる。
「1975年、学生時代にレコード店でアルバイトをしていました。
そのとき入荷してきたのが、ウェイン・ショーターの『ネイティブ・ダンサー』です」
ジャケットは青空にヤシの木。
南国を思わせるその佇まいに惹かれ、レコードに針を落とした瞬間、流れてきたのがミルトン・ナシメントの声だったという。
「1曲目の『ポンタ・ヂ・アレイア』ですね。
聴いた瞬間に、これは何だ!?と思いました」
ロック、ブラックミュージック、ジャズと幅広く聴いてきた中原さんにとっても、それはまったく新しい感覚だった。
「メロディーラインは童謡のようでもあり、同時にキリスト教の聖歌のようにも聞こえたんです。
実は親がカトリックで、子どものころから教会でラテン語の聖歌を耳にしていたので、意味は分からなくても、音として体に染み込んでいたものがあったのかもしれません」
言葉を超えて、音が直接心に入ってくる。
その体験が、ブラジル音楽への扉を開いた。
「違和感ではなく、すっと自分の中に入ってきたのを覚えています。
声の魅力に完全に引き込まれましたね」
レコードを手がかりに、想像力で音楽を旅する
当時はインターネットもなく、情報は極端に少なかった時代。
「アーティストに関わるデータなんてほとんどない。
だからこそ、音そのものがすべてでした」
数少ない雑誌の特集や解説には誤りも多かったが、それも含めて想像力をかき立てるに十分な材料だったという。
「正確な知識よりも、音を聴いて、そこから勝手に風景を思い描く。それが何より楽しかった」
1970年代後半、日本では第一次ブラジル音楽ブームが起こり、レコード会社から多くの作品が発売された。
「発売されたものはサンバ系が中心でしたが、僕ミルトン・ナシメント、ジョルジ・ベン、ジルベルト・ジル、カエターノ・ヴェローゾといった、いわゆる ブラジルのポップスの入口になるレコードを聴き始めて、どんどん深みにハマっていったという感じです」
その以降、LP、カセット、MD、DATと時代とともに媒体は変わっていたが、音楽との向き合い方の本質は変わらなかった。
ラジオとともに歩んだ、音楽の裏方人生

Photo:O-DAN
学生時代のレコード店でのアルバイト経験は、その後の進路にもつながっていく。
「放送業界に行くと決めたときから、テレビではなくラジオだと思っていました。
中高生のころ、洋楽番組をイヤホンで聴いていて、完全にラジオ育ちです」
1977年、FM東京(現・TOKYO FM)で番組制作に携わることになり、大学を中退して現場に飛び込んだ。
「不思議とミュージシャンになりたいわけではなかった。自分の技術では無理だと分かっていたので、裏方として音楽を支える道を選びました」
音楽を愛しながら、音楽の現場を支える。
その姿勢は、今も変わらない。
若い世代と音楽をつなぐために

Photo:O-DAN
かつては学生バンドのライブに足を運び、若い音楽家たちのステージを支える活動も続けてきた。
「音楽が好きな若い人たちが立てる場所を用意する。
それが何よりうれしかったですね」
一方で、近年は音楽を取り巻く環境の変化も強く感じているそうだ。
「趣味が多様化して、音楽が入口になりにくくなっている。ポルトガル語を学ぶ人にとって、ブラジル音楽は本来とても良い教材なんですけどね」
それでも、中原さんは音楽の力を信じている。
「楽しめることは、まだまだたくさんある。
音が持っている力は、時代が変わってもなくならないと思います」
音を頼りに、想像力で世界を広げてきた50年。
その原点には、今も変わらずミルトン・ナシメントの声との出会いが大きなチカラとなっている。
【新刊情報】
2026/1/22発売
太陽に撃ち抜かれて
ジョヴァーニ・マルチンス (著)/福嶋 伸洋 (翻訳)
世界10カ国で翻訳された
ブラジル発、新リアリズム(ノーヴォ・ヘアリズモ)